犬は人間を変える⁈
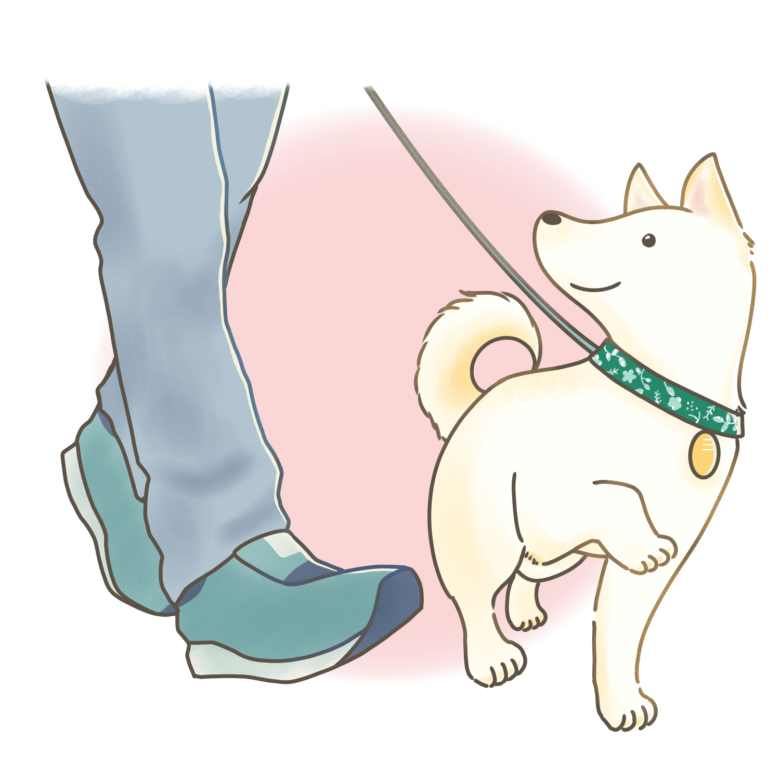
こんにちは、2匹のトイプードルを飼っているカトラです。
我が家で犬を飼い始めて7年。
子犬の頃のコロコロとしたかわいさやはしゃぎまわっていた様子は随分と落ち着き、6歳、7歳の2匹との生活は食事、散歩、癒し(くつろぎの時間)などほぼお決まりですが、家族として過ごす平和な日常の繰り返しです。
「私たち家族は犬を飼っている」と言いますが、「犬たちからたくさんの幸せをもらっている」実感があります。
今回は犬と人間のこの不思議な関係のお話です。
我が家の場合と、近所のおじさんの場合を例にしていきます。
この記事を読むと、犬を飼いたくなってしまうかもしれませんよ。
近所のおじさんが若返っている?!
どこのおうちでも犬の散歩はだいたい同じ時間にしているため、犬の散歩中の人とは毎回会う確率が高いです。
実は、数年前からよく合うおじさんと柴犬っぽい犬がいます。
おじさんによると、
その犬は保護犬(メス、雑種、当時5歳くらい)である
まだ家に慣れておらず時々脱走していなくなっていることがある
おじさんは(70歳くらい?で)足腰が痛くて散歩がたいへん
おじさんの家で犬の散歩ができるのはおじさんだけ(引っ張る力が強い)
毎日散歩から帰るとおじさんがお風呂に入れている(でも、外飼い)
犬は家族の中でおじさんにだけ心ゆるしている(おじさん談)
なぜ、おじさんがその犬を飼い始めたのかというとおじさんの息子(40歳代で仕事忙しい)が引き取ってきたから仕方なく、とのこと。
脱走しても戻ってくる
おじさんの家は外飼いをしているそうですが、知らぬ間に何かの拍子にリードを外して(抜けて?)脱走してしまうことがあるそうです。
最初は慌てて探しに回ったけれど、見つからず諦めて家にいると、いつの間にか数時間後にはちゃんと戻ってきているんですって。
ある日の散歩中なぜか、うちの犬がその犬に吠えてしまい、おびえたその犬がリードを外して目の前で逃げ出したことがあります。
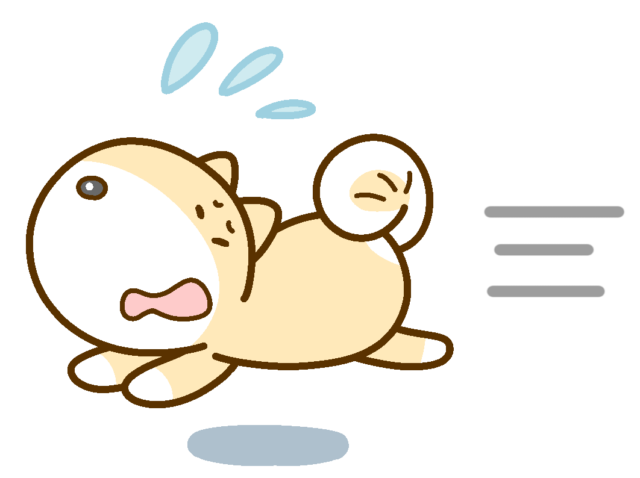
逃げたといっても、田んぼの中の散歩コースですから、田んぼ1枚分2,30メートルほど先に行って、止まっています。
そこでおじさんすかさず「レイコ~」と犬の名を叫び、呼び戻そうとします。足腰が痛いおじさんはあまり動けず、大きな声で繰り返し呼びつづけます。
しかし、何度呼んでもレイコちゃんは戻ってきません。まぁ、それ以上遠くにも行かないんですけどね。
私たちはレイコちゃんを怖がらせないようにそのまま帰りましたが、後で聞いたら、レイコちゃんが戻ってきたのは1時間くらいしてから、だったそうです。
おじさんとレイコちゃんの距離感はまだ信頼関係を築いている途中という感じでした。

雨の日も雪の日も散歩をしているおじさん
我が家は天気が悪い日、犬の散歩はしないので、
外でしか排泄しない犬や運動不足解消のために毎日欠かさず散歩をさせる飼い主さんってすごいと思います。
そして、この足腰が悪いおじさんも、毎日、たとえ天気が悪くてもカッパを着て犬と散歩しています。
しかも、私たちが合う時間帯だけでなく、決まって朝晩1日2回、散歩をさせています。
おじさんがもしも万歩計をつけていたら、きっと毎日1万歩以上は歩いているでしょう。
おじさんがまっすぐ歩いてる
2,3年経ったある日、おじさんの様子をあらためて観察すると、ずいぶん健康そうに見えました。
そうですよ、初めて会ったときは腰が曲がり、いかにも膝や腰が痛そうだったんですが。
今や姿勢がまっすぐになり、足取りも早く、スリムになって元気に歩いています。
もちろん、犬との距離感も近づいた様子。
そこで、やっと私は気が付きました。犬がおじさんを歩かせていたんだ。
おじさんの健康増進に犬との散歩が大きく影響していることは一目瞭然。
おじさんの話によると、「息子が保護犬を相談もなく連れてきた。」ということだったけれど、おそらく息子さんは「定年後の父親を心配して、運動させるために犬を連れてきた。」のではないかと想像します。
そして、当初からおじさんがその犬のことをかわいがっていたのは、そんな息子さんが連れてきた犬だという理由もあったのでしょう。最初は、名前を呼んでも戻ってこないような犬だったのですが、犬が先に歩いて後からおじさんが引っ張られながら後ろからついていく以前の散歩風景とは変わり、今はおじさんとレイコちゃん一緒に歩いています。
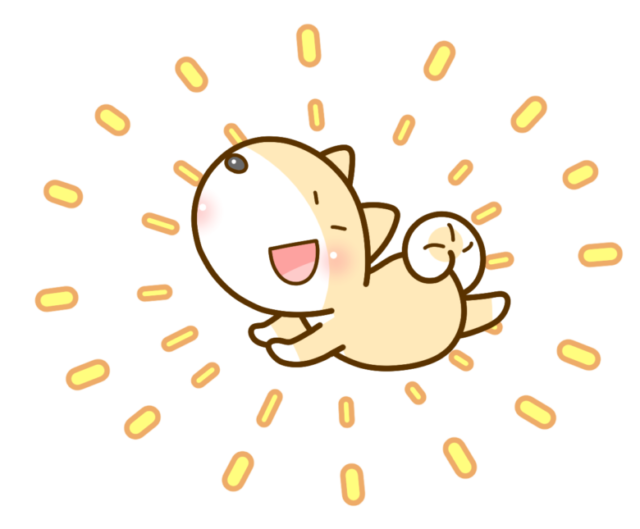
広告
ペットとの暮らしから得られる効果
ペットと暮らすことが人に与える効果として、身体的効果、心理的効果、社会的効果があるとちゃあんと研究で明らかになっています。
身体的効果
先ほど紹介したおじさんが「身体的効果」の実証例ですね。
曲がっていた腰や不安定な歩行が、数年後にはかなり安定し、見た目も若返って見えるほどでした。
義務的な運動だけではこうはならないでしょう。
やはり、「わんちゃんの散歩」だったからこその効果だと思います。
しかも、犬などペットを飼っている高齢者の「介護保険の利用が少ない」、つまり、ペットを飼っていると散歩などで運動量が増え介護予防になったり「飼う」という責任感からなのでしょうか、実際に「介護費の軽減」にも効果あると健康長寿医療センター研究所が明らかにしました。
実際にいくつかの研究では、血圧や心拍数の安定、血中コレステロールや中性脂肪の低下といった数値が改善している変化も明らかになっていますし、「オキシトシン」という幸せホルモンが増加していることもわかっています。
我が家でも、犬と散歩するだけでなく、餌やりや遊びなどの基本的なお世話も日課になりますので、私たちの生活サイクルも安定し、乱れがちな生活習慣の改善に効果的なんじゃないかなぁ。
心理的効果
犬を飼うことによる心理的効果は、人によって異なるかもしれませんが、「オキシトシン」という幸せホルモンが増加していることからも絶対にあると確信していますが、
犬と一緒に暮らしている方の多くが、ストレスや不安が癒されるような効果を実感しているのではないでしょうか?
全幅の信頼と全身全霊で私たち飼い主を愛してくれるわんちゃんですが、「ドックセラピー」というお仕事で人間を癒してくれているわんちゃんもいますよね。
我が家では息子たちが7,9歳の頃から犬を飼い始めましたが、一緒に遊んだり、エサをあげたり、ウンチを片づけたり、とお世話を通して、忍耐力や生き物への愛情や責任を学んでいたと思います。
そして、私がトイプードル2匹と暮らす中で感じたのは、「同じ犬種でも性格が全く違う」ということ。
個体によって性格が違い、好きなこと、喜ぶこと、嫌がること、愛情表現なども異なる。犬でさえ違うのだから「人間の兄弟」なら無論のこと、同じ両親、同じ環境で育っても性格や得意なことが異なって当然、ということが心から理解できました。
同じ屋根の下に住む兄弟だからこそ、親の対応を変えてはいけない(差別しない)と思い込んでいたのですが、犬を飼うことで「個によって得意なことも違うのだから、伝え方も個に合うように変えていい(区別する)」とわかり、今まで無意識に兄弟を比較していたことを反省できたし、「子育てのモヤモヤ」がすっと消えたんです。
社会的効果
犬がいると、子どもも夫婦も一緒に散歩に行ったり、犬の話題で会話したり、家族時間が増えコミュニケーションのきっかけとなります。
また、犬の散歩などで外出することで、散歩中やドックランの公園などで飼い主さん同士の交流の機会が増えますし、たとえその場にペットたちが居なくても動物好きの話題や話のきっかけとして、場を盛り上げたり、関係性を円滑にしてくれます。
さらに、SNSが発達した現代社会では、ペットの話題を通して新たな人々と知り合うきっかけが増えているようです。
犬を飼うことによる効果って本当にいろいろあります。
広告
感染症の危険性と災害時の対応
一方、犬を飼っていて心配なことは、病気と災害です。
新型コロナは犬にも感染すると言われていますし、災害時は避難場所への動物の同伴の可否が心配です。
避難場所へペット同伴が許可されない場合、犬と一緒の家族は屋外避難が多いですよね。
飼い始めの時に注意されていたので、狭いゲージ内で過ごせることと、どこでもおトイレができることは訓練して来たので、我が家の犬たちを避難所へ同伴しても大きなトラブルは起こさないと思うのですが、仮に同伴避難がOKだとしても、環境の変化による犬のストレスもあるでしょうし、トイレの臭いや鳴き声などやはり気を遣うため、ちょっと離れた場所を探すと思います。
犬を飼っていて感じるデメリットはそのくらいでしょうか・・・・

まとめ
スヌーピーのお話で、ドキッとした会話があります。それは、スヌーピーの飼い主(?)チャーリーブラウンとその親友ライナスの会話。
チャーリー・ブラウン
「人はなぜ犬を飼うんだろう?」
ライナス
「安心のためじゃないかなあ・・・ 世界中で少なくともひとつの生きものだけは自分を好きだと知ることの安心感」
私、ドキッとさせられ、うんうん、とうなづきまくりました
(*・ω・)(*-ω-)(*・ω・)(*-ω-)ウンウン♪
犬は、「無条件の愛」を与えてくれる存在です。飼い主その人が何者であるかに関わらず、社会的役割や肩書を超えて、何か大きな失敗をしてしまったとしても、それを批判せずに、その人のあるがままを受け入れてくれます。気の置けない友人関係でも、それはかなり難しいことです。ペットは、その飼い主がその人であるがゆえに愛を注いでくれるのです。
上記の高齢者の介護費削減の話につながると思いますが、犬と飼い主との関係は言い方を変えると、飼い主が愛情を注いだり、世話をしたりする対象に犬がなってくれているともいえます。
つまり、人にとって誰かに必要とされることが、その人の幸福感を満たしたり、孤独感を軽減したり、自尊心を高めてくれたりするのです。
子育ては自立して生活できることを目標にしているので、いつか離れることを前提にしていますが、犬たちとは最期まで一緒だよ、という気持ち。私が動けば一緒についてきて、帰ってくると尻尾を振りながら喜んで迎えてくれる。犬からの「感謝」「信頼」といった「無条件の愛」をモロに受けられる日々は、私の幸せです。

広告
3年後の追記
悲しいことがありました。
我が家の2匹のトイプードルのうち、下の子が亡くなりました。9歳でした。
死因は腎臓の病気でしたが、私がその子の体調変化に気付くのが遅く、受診が遅れてしまい、10日間病んで臥せっただけで亡くなりました。
慢性腎不全は長い経過をたどり腎臓の働きが徐々に低下して腎不全に至ります。
初期は無症状な期間がありますが、その後、飲水量が増え、尿量が増す多飲多尿の症状が現れます。
我が家の犬も多飲多尿の時期があったのですが、夏の暑さで多く飲んでいるのだと思い込んでしまったことと、父の入院介護で私が忙しく家を留守にすることが重なり、早く受診させてあげることができませんでした。とても悔いています。下痢と嘔吐により受診した時には数値的には腎不全ステージ4というかなり悪い状態。
そこからは夫も仕事を休んだり調整をつけたりして私か夫が24時間ずっと一緒に過ごしました。
最期の瞬間は、病院の診察台での点滴処置を終え、夫の腕の中に納まったときでした。
突然ぴくぴくと痙攣したように体を硬直させたので、すかさず聴診器をあてた獣医さんでしたが、「これ以上は…」と、私たちも同意しました。
最期まで飼い主思いで優しい犬でした。
日に日に弱っていく愛犬を受け入れられず、私たちは毎日点滴をしたり、細い注射器で口の中にドックフードを流し入れたりしました。それが良かったのかどうかはわかりませんし、もしかしたら命を縮めてしまったのかもしれません。
でも、愛犬は10日間も私たちの悔いが残らないようにやらせてくれ、それに応えるように頑張ってくれて、最期の瞬間も私たちが見守っていることを確認したかのように心臓の鼓動を止めたのです。
おかげで後悔はほとんどないし、それ以上に9年間の楽しい愛犬との思い出に感謝しかありません。
もちろん、愛犬ロスがあり寂しくて涙が止まりませんが、4ケ月経ち、時薬(ときぐすり)のおかげでこのように文字に書けるようになりました。そして何より、もう1匹の犬が私たちを慰めてくれていますから。
最後に
今回、お伝えしたいのは、犬を飼う責任の中には、言葉で伝えられない犬の体調変化に気づくこと、が含まれているということです。
医者ではないので診断をつけることはできませんが、飼い主だからこそ「普段と違う犬の様子」がわかるはずです。
そして、私はこの普段と違う様子を気づいていたのに受診をさせなかったことを悔いています。
飼い主さんはおそらく小さな「犬の体調変化」でも容易に気が付いているんじゃないかな。
なのに、飼い主である私たちはそれが年齢のせいとか、暑さのせいにして納得しようとしてしまう癖があるんです。
「あれ?」と思ったら、飼い主としての直感や感覚を大切にすべきです。
でないと、私のように悔いが残ることになってしまいます。できれば、気になることが気楽に相談できる獣医さんがいるといいですね。
追記2ペット保険について
ついでにもう1つ。我が家はペットの保険に入っていました。
今回、10日間の検査治療で約10万円かかりました。
我が家は儲け度外視の獣医さんにお世話になっているため、低料金だったと思いますが、まとまった出費になったのは間違いありません。
我が家が加入していたペット保険の保障割合50%でしたから、今回かかった医療費のほぼ半額が戻ってきました。
もともとは、うちの犬が誰かを噛んだり転倒させてケガさせたりした場合に備えて加入したペット保険ですが、今回は愛犬自身のために使うことができました。
保険加入していたことで、「悔いの残らない医療を受けさせる」ことができたと思っています。
保険加入について、犬を飼い始めるときの参考にしていただけたら嬉しいです。